2011.12.10 皆既月食
2011.12.10 21h45mから12.11 1h18mにけけて、全国で皆既月食が見られた。
皆既の中心は23h32m。
前半は雲の多い天気だったが、皆既が始まるころから晴天になった。
今回の月食は地球本影の南側を月が通過したため、南側に明るい皆既月食だった。
 |
 |
 |
2011.12.10
皆既月食と地球本影
|
2011.12.10 23:36:54
500mm F5.6 1s |
2011.12.10 23:56:44
皆既中の星空 500mm 5s |
白樺峠 タカの渡り(2011.9.24)
今年は9月になってもタカの渡り数が極端に少く、天候も雨がちで、9/23から天候が回復した。9/23に松本平にタカの集結、9/24渡りを期待して、9/24に乗鞍白樺峠に行ってみた。早朝で、駐車場は全て満車の状態。人だけは年々増えていくみたい。
晴天で、公式記録では、5136羽(9/25は2003羽)の大量飛行だったが、松本平付近で上昇気流が発生していたらしく、遠くでタカ柱がな何度も発生し、白樺峠上空を飛ぶタカが少なく、写真撮影には不向きだった。
 |
 |
|
サシバ
|
ミサゴ |
|
 |
 |
 |
| タカの舞1 |
タカの舞2 |
タカの舞3 |
ミンミンゼミの緑型(2011.8.15)
夕方、庭の木に、見たことの無い、本体が緑色のセミが止まっているのをみつけた。
ネットで調べると、甲府盆地などに生息する、ミンミンゼミの緑型らしい。
完全に黒色部が無くなったものはミカドミンミンと呼ばれるが、この固体は黒色部分が少し残るかなり緑の濃いタイプのようだ。
 |
|
|
2011.8.15
|
|
|
オオムラサキ
このあたりで繁殖していると思われる、日本の国蝶 オオムラサキが、今年も現れた。我が家の周辺を元気よく飛び回っている。
近くの樫の木には、5〜6羽が群がって樹液を吸っている。
 |
 |
 |
2011.7.11
|
2011.7.11
|
2011.7.11
|
ノビタキの巣立ち雛
ママーァ、こっちこっち・・・といっているような・・・
 |
|
|
2011.6.22
野辺山牧場 |
|
|
 |
 |
 |
2011.6.22
ノビタキ♂ |
2011.6.22
ヒバリ |
2011.6.22
ヒバリ正面顔 |
戸隠森林植物園(2011.6.4-5)
1000円高速の終了も近づき、休日の戸隠森林植物園の大駐車場は、早朝すでにほぼ満杯。
アカショウビンは♀も到着して繁殖の時期にはいった。
3箇所ほどあるアカショウビン出現ポイントは、大砲レンズの三脚群で通行できないほど終日大混雑。平日に限る。
そこを避けてデジスコ撮影。
葉が茂りだし、声はすれども鳥を見つけるのは容易ではない。
 |
 |
 |
アカゲラ♂
デジスコ 1677mm |
コサメビタキ
デジスコ 1677mm |
ミソサザイ
デジスコ 2560mm |
 |
 |
 |
ニュウナイスズメ
デジスコ 2952mm |
ニュウナイスズメ
デジスコ 2952mm |
キビタキ♂
デジスコ 1931mm |
 |
 |
|
アカゲラ♀
デジスコ 980mm |
ノジコ
デジスコ 3500mm |
|
野辺山高原(2011.5.25)
野辺山高原は、初夏の農作業も終了し、静けさがもどった。
野辺山牧場には、ノビタキ、ホオアカ、コムクドリ、モズ、ヒバリなどペアでの行動が見られた。
カッコウの声はまだ聞えない。
 |
|
|
コムクドリのカップル
デジスコ 2220mm |
|
|
ガビチョウ(2011.5.9)
自宅周辺では、ホオジロ、ウグイスなどの美声が聞こえる。
そのなかでも、キビタキに似た、ひときわ大きく甘く明るい声が時々聞える。
どうも周辺で数年前から繁殖しているガビチョウらしい。
自宅2階の窓から、大きな芋虫を採食しているのが見えた。
 |
 |
 |
| デジスコ 2220mm |
デジスコ 2220mm |
デジスコ 2220mm |
キジの雄たけび(2011.5.3)
今年も、早朝、雄キジが北側田んぼの土手の上で、羽をばたつかせながら、ギョエーギョエーと雄たけびをあげる季節になった。7月になると、雌キジが雛をつれて歩き回るのが見られるだろう。
 |
 |
 |
| デジスコ 1677mm |
デジスコ 3500mm trm |
デジスコ 3500mm trm |
土星のハイリゲンシャイン効果(環の衝効果)
土星が衝の時期に、土星の環が通常より明るくなる現象が見られる。
環を太陽の光が当たっている方向から見ることになる衝付近では、環を構成している粒子の反射光が他の粒子に邪魔されない為に、環が明るく見えると考えられている現象で、ハイリゲンシャイン効果(環の衝効果)とも呼ばれている。
 |
|
|
| ハイリゲンシャイン効果 |
|
|
2011年度の土星
今期の土星は、4/5におとめ座で衝を迎え、夜半南のそらに輝いている。
冬の寒波による悪気流で、まともな像を見られなかったが、3月も終わりに近づき、春めい来るにつれて寒波も和らぎ、山麓でも気流も安定しつつある。土星面の気流の乱れによる大規模白斑はかなり拡散しているが、写真左下方に青白く見えている。
衝をはさんで、左側に見えていた本体の輪に写る影が右側に見えるようになった。
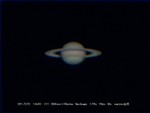 |
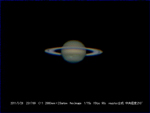 |
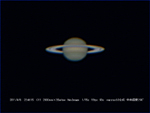 |
2011.2.23 1h5m
視直径 18.7" |
2011.3.28 23h17m
視直径 19.2" |
2011.4.6 22h46m
視直径 19.2" |
 |
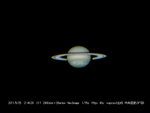 |
|
2011.4.14 22h59m
視直径 19.2" |
2011.5.25 21h49m
視直径 18.4" |
|
2011.3.28 春の雪
3月27日夜から降りだした雪は、翌朝までに5cmほど積もった。日中の晴天で、溶けるのも早い。
地震頻発(2011.3.11〜)
3月11日14時46分宮城沖でマグニチュード9.0の地震が発生した。
北杜市では震度5との報告だが、明野は、茅が岳の硬い粘土質土壌のせいか、震度3ぐらいの、大地でサーフィンしているようなゆっくりとした横揺れが5分ぐらい続いた。
直後から停電発生。
その後、少し弱めの地震が2度続いて発生した。
山中湖付近の震度5(山梨地方版で放映されただけ・・)と茨木沖の震度6クラス地震が発生したことを、停電のためテレビが映らず、携帯電話のワンセグで情報を得た。
被害は、ワイングラスが数個転がり落ちて割れただけで済んだが、停電は翌朝まで続いた。
12日2時ごろにまた地震が発生。今度は長野北部。
14日より、中央本線がストップしている。16日から間引き運転。小海線はいまだにストップ。
15日22時31分静岡東部(富士宮あたり)で震度6が発生。
明野は震度3ぐらいの縦型地震だった。被害無し。
3/16から輪番停電が実施中
・3/16 18:40〜20:40
・3/17 15:45〜18:40
・3/18 12:45〜15:30
・3/19 実施せず
・3/20 実施せず
・3/21 実施せず
・3/22 15:45〜18:30
(最も電力消費の多い、東京都区部は停電対象外。地方はその尻拭い。そろそろ頭にきだしたぞ。境目住民から火の手が上がるだろう。)
・3/23〜28 実施せず
木星と土星(2011.2.22)
寒波が和らぎ、気流の乱れも若干落ち着いてきた。
木星は日没時西に低く輝き、今シーズンも終わりに近づいている。
木星表面の、SEBの復活はかなり進み、この位置(中央軽度 50゚(II)付近)では、中央部の淡い帯状に見える。来期には完全復活するだろう。
土星は夜半には南の空に輝くようになった。春の安定した気流になり、観測の好機を迎える。輪も傾き、見栄えがするようになった。秋に発生した北半球(写真の下側)の白斑は大きく拡散している。
 |
 |
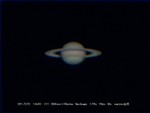 |
木星 2011.2.22 17h38m
|
木星 2011.2.22 18h11m |
土星 2011.2.23 1h5m |
2011.2.15 大雪
年明け以来晴天が続いていたのが、突如、2/11(今冬初積雪:20cm)に続き、2/14夜から降り続いた雪が、30cmほど積もった。除雪が大変だ。
 |
 |
|
背景は甲斐駒
|
|
|
山中湖にレンジャクがやってきた(2011.1.20)
昨年はやってこなかったレンジャクが、山中湖にやってきた。
例年なら、2月中旬〜3月中旬にやってくるのが、今年は早々と、1月7日ごろ、
ヒレンジャクの20羽ほどの群れがやってきて、長池の宿り木の実を食べ、滞留してるので、見に行ってきた。
キレンジャクはいつくるのだろうか・・・。今年の宿り木の実は不作気味のようにみえるので、ヒレンジャクに食べつくされてしまうかも・・・。
青空を背景に、鳥が綺麗に映えるが、逆に、枝の影の入り込みを避け、目にキャッチライトをいれるのは大変だ。
 |
 |
 |
| 整列 |
枝の影が入って残念 |
|
 |
 |
 |
|
宿り木の実を食べる |
コブハクチョウ |
木星のSEBの復活の状態(2010.11.27〜)
冬の悪気流の影響で、ほとんど観測不能状態ではあるが、何とか観測できた記録を 星−木星 のページに移した。
|
|
|