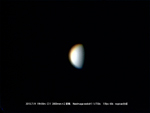◆金星
2011年〜2012年の金星
2011年8月15日に外合となった金星は、夕方の西空に移り、年末頃から夕方に見られるようになった。
2012年3月27日東方最大離角(半月状)、4月30日最大工期光輝(三日月状)、6月6日内合。
2012年6月6日の内合時は、金星の日面通過が見られた。
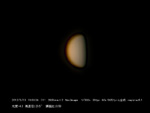 |
 |
 |
 |
| 2012.3.13 (視直径 20.5") |
2012.4.10 (視直径 27.8") |
2012.4.24 (視直径 32.8") |
2012.5.7 (視直径 41.5") |
 |
 |
 |
|
| 2012.5.11 (視直径 44.2") |
2012.5.16 (視直径 47.8") |
2012.6.6 (視直径 57.8") |
金星(2010.5〜10)
望遠鏡:セレストロン C11 (シュミットカセグレン D=280mm F10) SXD赤道儀に搭載
×2エクステンダー直焦
カメラ:セレストロン NexImage webカメラ 15fps 60s(900フレーム) Registax5 コンポジット ウエーブレット処理
撮影地:山梨県北杜市明野町自宅
写真は下が北側(倒立像:望遠鏡で見た像)。
夕方、西空に宵の明星金星が明るく見えるようになった。
8/20の東方最大離角(半月状に見える)、10/28の内合(新月状)にむけて、次第に、細く大きく見えるようになる。
・7/10 1ヶ月ぶりの梅雨の間の星空。日没10分後の撮影。気流が悪い。半月状で、幾分大きくなった。
・8/3夕方まで晴天猛暑、雲が広がりだして、夜半雨・・・が続く。日没時の高度は低いが、明るいので、日没前の気流が安定している時に撮影できるのが救い。
・8/20東方最大離角を迎えたが、地上高度は大変低い。太陽の出ているうちに撮影しないと、気流の乱れでまともな像を得る事は難しい。夕方から曇り・雨になる天気が続いている。
・
金星(2009.2〜3)
望遠鏡:ビクセン102mm屈折(フローライト 910mm) SPDX赤道儀に搭載
×2エクステンダー、NP12mm
カメラ:NIKON Coolpix4500 32mmコリメート ISO400
撮影地:山梨県北杜市明野町自宅
夕方、西空に金星が明るく輝いている。望遠鏡では、3月の中頃まで(3/25内合)まで、半月状から細い三日月になるのが見える。
冬の空は、透明度は良いが、気流は最悪。写真に撮れるのは、気流の収まった一瞬しかない。
写真は上が北側(正立像)。
 |
 |
 |
| 2009.2.2 半月状の金星 |
2009.2.17 三日月状の金星 |
2009.3.2 |
 |
 |
|
| 2009.3.10 細く光る金星 |
2009.3.15 内合10日前 |
金星(2002.8〜10)
望遠鏡:ビクセン102mm屈折(フローライト 910mm) SP赤道儀に搭載
×2エクステンダー、PL7.5MM
カメラ:NIKON Coolpix990 23.4mmコリメート ISO400
画像処理:Photoshop で、2048×1536pixel を 800×600pixel に画像解像度変換実施
撮影地:山梨県明野村自宅
写真は下が北側(倒立像)。
 |
 |
 |
 |
| 2002.8.30 18h18m 1/125s | 2002.9.17 17h11m 1/125s | 2002.10.4 17h04m 1/30s | 2002.10.12 16h37m 1/125s |
金星・木星・三日月の接近(2008.12.1)
夕方の西空に、金星と木星と細い月が接近した。
背景の山は南アルプス(右端の山は甲斐駒ヶ岳)。
 |
| 2008.12.1 金星・木星・三日月の接近 |
 |
| 南アルプス地蔵岳に沈む金星 2002.9.19 18h35m NIKON D1 260mm |